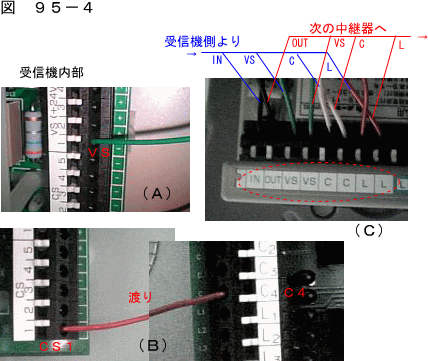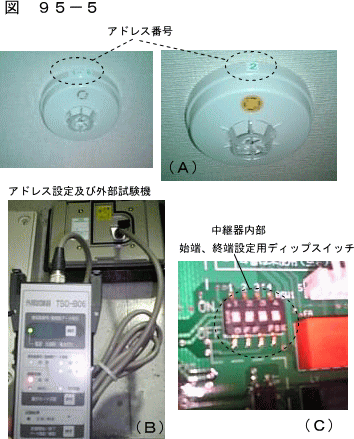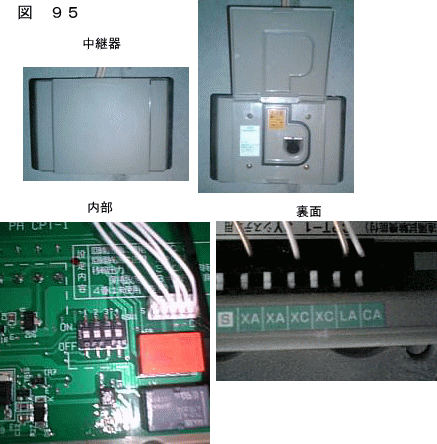
マンションなどでは住戸内に立ち入らなくても感知器の点検が出来るように外部試験機能付の感知器を設置することが多くみられます。
専用の感知器と中継器を使用します。(ホーチキ社製CPT−1)
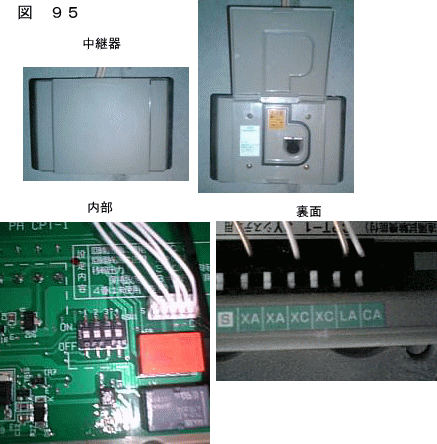
中継器には主に次のような端子があります。
OUT、IN、VS、VS、L、L、C、C、LA、CA、XA、XCなどです。(図 95−2)
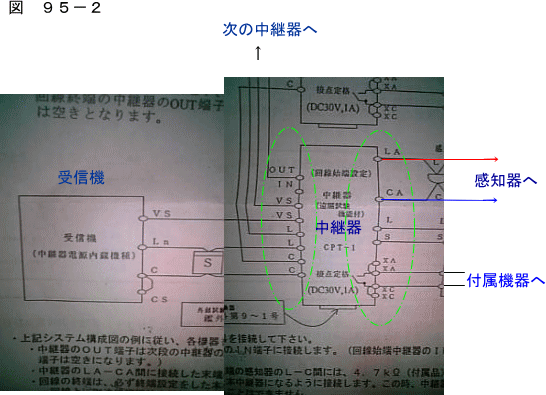
配線の例。(図 95−3)
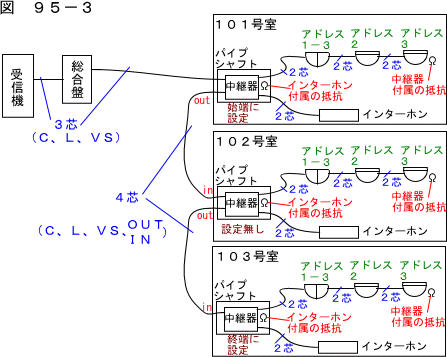
受信機は中継器に対応するためにVSの端子がある特殊な受信機を使用します。(図 95−4 A)
受信機内部でCとCSを接続します。(図95−4 B)
受信機のVS端子から全ての中継器のVS端子に渡るように結線します。(図 95−4 C)
受信機のC、Lを送り配線で中継器に接続します。(図 95−4 C)
配線のルートの上で受信機に一番近い(101号室)中継器のOUT端子と次の(102号室)中継器のIN端子を接続し、(102号室の中継器の)OUT端子と次の(103号室)中継器のINの端子を接続して行きます。よって最後の(103号室の)中継器のOUT端子と最初の(101号室の)中継器のIN端子は空き端子になります。(図 95−4 C)
この中継器を使用する場合、通常使用する10kΩの終端抵抗は使用しません。ただし中継器内部のディップスイッチで配線ルートの上で受信機に一番近い(101号室の)中継器を始端に、一番遠い(103号室の)中継器を終端に設定する必要があります。(図 95−5 C)この場合103号室の中継器のC、L端子の一つずつは空き端子になります。
中継器のLA、CA端子から感知器のC、L端子に送り配線で結線します。終端になる感知器には中継器に付属されている終端抵抗を接続します。
感知器は設定器を用いて各住戸ごとに1番から順に2、3・・・とアドレスを設定する必要があります。(図 95−5 B)また1番の感知器を設定する際に、その住戸に全部で何個の感知器が設定されているのかをも設定しなくてはなりません。つまり合計3個の感知器が設置されている住戸の1番の感知器には1−3と設定する必要があります。(図 95−5 A)
配線の終端となる感知器には中継器に付属されている終端抵抗を接続します。必ずしも終端抵抗を接続する感知器がアドレスの3番になる必要はありません。また中継器から一番近い感知器のアドレスを1番にする必要もありません。重要なのはアドレスが重複しないことです。
中継器のXA、XCからは感知器作動時にA接点が出力されるので、A接点を入力して作動する付属機器(インターホン等)に接続することで感知器とインターホンを連動させることが出来ます。